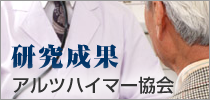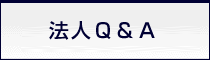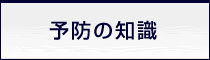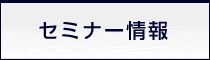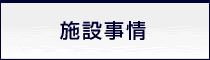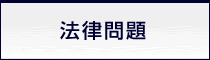認知症について
急速に高齢化が進む日本、認知症問題は患者のみならず、家族など患者を取り巻く環境も含め対策を取るべき大きな社会問題となっております。
平成22年厚生労働省発表の「認知症高齢者数」は日常自立度Ⅱ以上で280万人と発表されています。
この人数は65歳以上の人口に対する約10%であり、今後もさらに増え続けるといわれています。
自分、家族だけは認知症にならないなどとは思わず、日常生活から予防に心がけ、注意を怠らず普段とは違う物忘れなど気になることがあれば専門医の診察を受けることが大切です。 |
認知症を引き起こす病気
| 認知症を引き起こす病気は多数あります。中高年の方で認知症の症状が現れた場合、「アルツハイマー型認知症」、「脳血管性認知症」の可能性を考えることが必要です。認知症を引き起こす病気の中で、この2つの病気が最も多く見られます。それぞれ予防方法や治療方法が異なりますので、専門医にご相談ください。 |
アルツハイマー型認知症とは
脳の萎縮、老人斑、神経原線維変化、神経細胞の脱落
脳の神経細胞が急激に減ってしまい、脳が萎縮して(小さくなって)高度の知能低下や人格の崩壊がおこる認知症です。
初期の症状は、徐々に始まり、ゆっくり進行するもの忘れが特徴です。古い記憶はよく保たれますが、最近の出来事を覚えることができません。そのため同じことを何度も何度も聞きかえしたり、置き忘れが多くなります。昨日お礼の電話をしたことを忘れて今日また同じ相手に電話などということがあります。
抑うつや妄想ではじまることもあります。 |
脳血管性認知症とは
脳血管性認知症では、障害された部位によって症状は異なり、めまい、しびれ、言語障害、知的能力の低下等にはむらがあります。また、記憶力の低下が強いわりには判断力や理解力などが相対的によく保たれている場合(まだら認知症)があります。また、症状は日によって差が激しいことがあります。
この病気は高血圧、糖尿病、高脂血症や血液が凝固しやすい人、ストレスのある人によく起こり、これらの状態を危険因子と呼びます。 |
|
 |
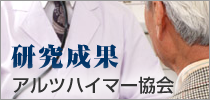

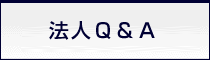
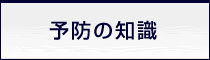
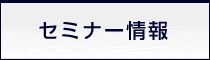
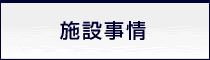
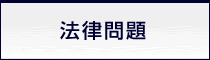
|